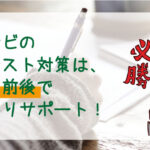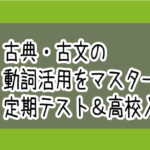【中学理科】心臓と血液の流れをわかりやすく解説!体循環と肺循環のしくみをマスターしよう!
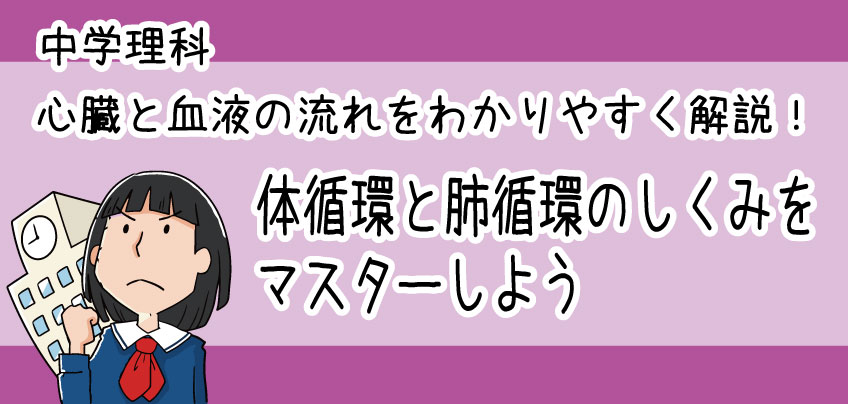
心臓と血液のしくみ、きちんと理解できていますか?
中学理科の「生物分野」で登場する心臓と血液の流れは、体のしくみを学ぶうえでとても重要な単元です。「心臓には4つの部屋があるって覚えたけど、どっちが右でどっちが左?」「体循環と肺循環って何が違うの?」と混乱してしまう中学生も多いのではないでしょうか。
この単元では、心臓の構造や血液の循環経路、血管の種類とその特徴、血液の成分と役割など、多くの知識を“立体的に”理解する必要があります。しかし、テストでは図を使って説明されたり、流れの順序を問われたりと、単なる暗記だけでは乗り越えられない難しさもあります。

このコラムでは、中学理科で学ぶ「心臓と血液の流れ」について、基礎から丁寧にわかりやすく5つの章に分けて解説します。苦手意識を持ちやすい単元こそ、仕組みを「イメージ」しながら学ぶことが理解への近道です。
「なるほど、そういうことだったのか!」と納得できる構成でお届けしますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
心臓の構造と働き
心臓は、私たちの体の中で常に休まず働き続けている「血液のポンプ」です。1分間に約70回、1日に約10万回も収縮と拡張を繰り返し、血液を全身に送り出しています。そんな心臓の構造は、実はとてもよくできていて、4つの部屋(右心房・右心室・左心房・左心室)に分かれています。
まず、心臓の「右側」と「左側」は、私たちから見たときの左右ではなく、心臓本人の右と左で考えるのがポイントです。つまり、図で見ると左右が逆に見えるため、混乱しやすいところです。
心臓は、1回の収縮で左右同時に血液を送り出し、リズムよく循環させることで、全身に酸素と栄養を届け、不要な二酸化炭素や老廃物を回収する働きをしています。
右心房・右心室
【右心房】は、全身を回ってきた血液(酸素が少ない血液)を受け取る部屋です。その血液は次に【右心室】へ送られ、肺に向かって送り出されます。肺では血液が酸素を受け取るため、ここで酸素が多い状態に変わります。
左心房・左心室
肺で酸素をたっぷり取り込んだ血液は、【左心房】に戻ってきます。そして、【左心室】から今度は全身に送り出されるのです。左心室の壁は特に厚く、全身に血液を送り出すための大きな力を生み出しています。

ハカセ
血液の循環路
血液は、酸素と栄養を体中に届け、二酸化炭素や老廃物を回収するという重要な役割を持っています。そのために、心臓から送り出されて体をめぐり、また心臓に戻ってくる「循環」の仕組みが必要です。中学校の理科では、この循環経路を「体循環」と「肺循環」の2つに分けて学びます。
スタートと目的地に注目!
体循環は心臓の左側から全身へ、肺循環は心臓の右側から肺へと血液が流れる経路。役割と流れを図で理解しよう。
【体循環】は、心臓の左心室から酸素をたっぷり含んだ血液を全身に送り出し、身体のすみずみで酸素と栄養を届けます。その後、酸素を使い終えた血液(酸素が少なく二酸化炭素が多い状態)が心臓の右心房へ戻ってくるという流れです。
一方、【肺循環】は右心室からスタートし、血液を肺へ送り、肺で酸素を取り込んでから左心房に戻ってくる流れです。
循環路はつながっている
体循環と肺循環は別々に覚えるのではなく、「一つの大きなループ」として理解するのがポイント。体循環と肺循環は、まるで2つの輪がつながっているようなしくみになっています。たとえば、肺で酸素を受け取った血液はそのまま体の隅々へ運ばれ、役目を終えたらまた肺へと戻る、という流れを絶え間なく繰り返しているのです。このループがうまく働かないと、酸素不足や老廃物の蓄積が起こり、健康に影響を及ぼします。だからこそ、血液循環は私たちの命に直結する重要なしくみなのです。

ハカセ
動脈と静脈の特徴
血液が心臓から送り出され、また心臓に戻るには、「血管」が必要です。血管は大きく分けて3種類あり、それぞれに異なる役割と構造があります。ここでは主に、動脈と静脈の違いに注目して、血液がどのように運ばれているのかを理解していきましょう。
動脈は「送り出す」、静脈は「戻す」
動脈は心臓から血液を送り出す、静脈は心臓に戻すという“流れの向き”が最大の違い。
【動脈】は、心臓から送り出された血液を全身に運ぶ血管です。高い圧力に耐えられるように、血管の壁は厚く、弾力があります。最も太い動脈は「大動脈」と呼ばれ、左心室から出て体のすみずみへと血液を届けます。
【静脈】は、全身を回って酸素を使い終えた血液を心臓に戻す血管です。動脈と比べて壁は薄く、逆流を防ぐ「静脈弁」が付いているのが特徴です。血液が重力に逆らって心臓に戻るため、弁が一定方向にしか開かない構造になっています。
毛細血管がつなぐ“命のやりとり”
動脈と静脈の間にある毛細血管が、酸素・二酸化炭素・栄養などのやり取りをする場。【毛細血管】は、動脈と静脈の中間にある非常に細い血管です。血管の壁がとても薄く、血液の成分が細胞とやりとりできる構造になっています。
たとえば、肺の毛細血管では酸素と二酸化炭素の交換が行われ、筋肉の毛細血管では酸素と栄養が届けられ、老廃物を回収します。このように、毛細血管は血液が「仕事をする場所」であり、全身の細胞と密接に関係しています。

ハカセ
血液の成分と役割
血液はただの「赤い液体」ではなく、いくつかの成分がそれぞれ大切な役割を担っています。中学理科では主に赤血球・白血球・血小板・血しょうの4つを学びます。これらの働きをしっかり覚えることで、テスト対策にも役立ちます。
酸素を運ぶ赤血球
赤血球は血液の色を赤くし、酸素を運ぶという最も基本的な役割をもつ。
【赤血球】は、血液の中でもっとも多く含まれる成分で、ヘモグロビンという赤い色素を含んでいます。このヘモグロビンが酸素と結びついて、肺で取り込んだ酸素を全身の細胞に運びます。形は中央がくぼんだ円盤状で、弾力があるため細い毛細血管にも入り込めます。赤血球は「酸素の運び屋」として、全身の活動を支える重要な存在です。
白血球は「体を守る戦士」
白血球は体内に入った細菌やウイルスを攻撃する免疫機能の要。
【白血球】は、血液の中で数は少ないものの、免疫の働きを担うとても重要な細胞です。体内に細菌やウイルスが侵入すると、それを見つけて攻撃し、取り込んで分解(貪食)します。風邪をひいたときやケガをしたときに白血球の数が増えるのは、体が「外敵と戦っている証拠」です。まさに白血球は体を守る“戦士”といえるでしょう。
血小板と血しょうの働き
出血を止める「血小板」、運搬や体温調節を担う「血しょう」。
【血小板】は、ケガなどで血管が破れたときに集まって傷口をふさぎ、止血を助ける働きをします。血小板の働きがなければ、わずかな出血でも止まらず命に関わることもあります。【血しょう】は、血液の液体部分で、栄養・ホルモン・老廃物などを運んだり、体温調節の役割も果たします。血液の流れをスムーズに保つ潤滑液のような存在です。

心臓と血液の健康
私たちの命を支える心臓と血液のしくみですが、その働きがうまくいかなくなると、健康に大きな影響を及ぼします。心臓や血管の病気を防ぐためには、日々の生活習慣が非常に重要です。この章では、循環器系の健康を守るために意識すべきポイントを解説します。
心臓病や高血圧は“身近な問題”
心臓の働きに負担がかかると、命に関わる病気につながることもある。心臓は生まれてからずっと休まず働き続ける臓器です。その分、食生活や運動不足、ストレスなどが重なると、負担が大きくなります。
たとえば、高脂肪の食事を続けると血液がドロドロになり、動脈が詰まりやすくなります。これが原因で、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気につながることがあります。また、血管が硬くなる「動脈硬化」や「高血圧」も、心臓に余計な負担をかけてしまいます。
健康な血液循環のために
運動・食事・睡眠など、毎日の生活習慣を見直すことが第一歩。循環器系を健康に保つには、**「バランスのよい食事」「適度な運動」「十分な睡眠」**の3つが基本です。
- 野菜や魚を中心とした和食は、血管の健康を保つのに効果的
- ウォーキングや軽い運動で血流をよくする
- スマホやゲームの時間を減らし、しっかり睡眠をとる
こうした心がけが、心臓と血管の働きを正常に保つ鍵になります。
学びを「健康意識」に活かそう
学んだ知識を「自分の体のために使う」ことが理科の本当の意味。中学理科で学ぶ内容は、テストだけのためではなく、自分や家族の健康を守る知識にもつながっています。「血液が流れるから体が動く」「心臓が止まると命が止まる」――そんな当たり前のことを、実感として理解できるようになることが、理科を学ぶ意味でもあります。

心臓と血液のしくみを知ることは「生きること」を理解すること
中学理科の「心臓と血液の流れ」は、単なる暗記単元ではありません。心臓の4つの部屋や、体循環・肺循環の流れ、血管の役割、血液の成分など、すべてが私たちの体を支える仕組みとして深くつながっています。
また、こうした知識は、テストや受験だけでなく、自分の健康や家族の体を守るための“実生活で役立つ知識”でもあります。「どうしてバランスの良い食事が必要なのか」「なぜ運動が大切なのか」といった生活習慣の意識にもつながる大切なテーマです。
今回の記事を通して、「難しそう」と感じていた内容も、「なるほど」「わかったかも」と思えるきっかけになっていたら幸いです。心臓が送り出す血液の旅路を、仕組みごと理解することで、理科の世界がぐっと身近に感じられるようになるはずです。
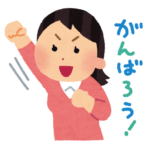

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。
当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。
まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 5,556人 に閲覧されています。
.jpg)