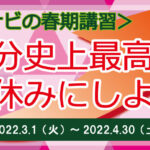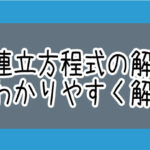【中学地理】雨温図で学ぶ世界の気候帯と特徴
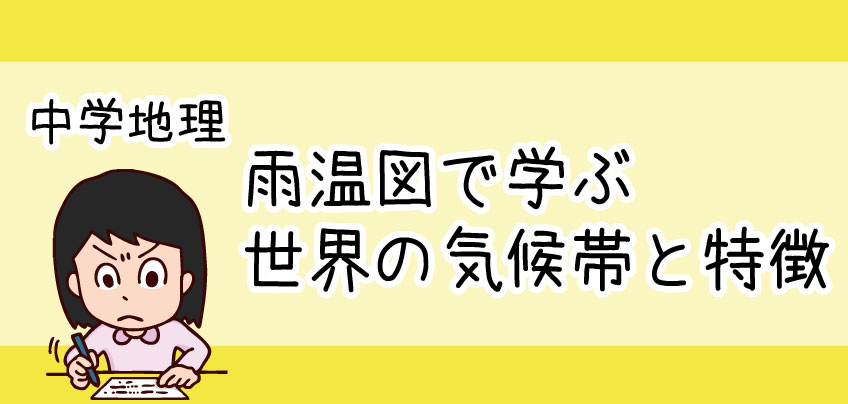

中学地理のテストでよく出る単元のひとつが「雨温図と世界の気候」です。
「この雨温図はどこの地域?」「気温と降水量の違いって何を意味してるの?」と、見慣れないグラフに戸惑う人も多いのではないでしょうか。でも、雨温図の見方さえわかれば、世界の気候帯を一気に整理することができます。テストや入試では、この“読み取り力”が得点のカギになります。
この記事では、雨温図の基本から、気候帯ごとの特徴と見分け方までを5つのステップでやさしく解説。地理がちょっと苦手…という人も、理解がぐっと深まります!

目次
雨温図とは?基本の読み取り方とポイント
社会の定期テストや高校入試で頻出の「雨温図」は、気温と降水量の変化を1年分まとめたグラフのこと。世界の気候を視覚的に比較できる便利なツールです。ただし、正しく読み取るにはいくつかの“コツ”があります。この章では、その基本を押さえていきましょう。
雨温図は「棒グラフ+折れ線グラフ」で構成される
降水量は棒グラフ、気温は折れ線グラフで表されていることを理解しよう。雨温図は、1月から12月までの1年間の平均気温と降水量の変化を表すグラフです。
-
棒グラフ=月ごとの降水量(雨の多さ)
-
折れ線グラフ=月ごとの平均気温
これらを見比べることで、「いつ雨が多いのか」「どの季節が暑いor寒いのか」がわかります。まずはどちらの線が何を示しているのかをしっかり確認することが大切です。
縦軸と単位に注意!スケールが違うと誤読の元
気温・降水量の単位と最大値に注目しよう。地域によってスケールが異なる場合も。雨温図を読むときは、縦軸の単位と目盛りの幅にも注意しましょう。特に降水量は、多い地域(熱帯)では最大1000mm以上、少ない地域(乾燥帯)では100mm未満という差があるため、グラフの大きさだけで判断するとミスにつながります。また、気温の目盛りも、寒帯ではマイナス温度まで表示されることがあるので、常にスケールの数字を確認してから読み取るようにしましょう。
1年の変化に注目して“季節感”を読み取る
気温の上がり方・下がり方から「南半球」「北半球」も判断できる!たとえば、6〜8月に気温が高ければ北半球、12〜2月に気温が高ければ南半球というように、気温の変化から季節をつかむことも可能です。さらに、降水量が特定の時期に集中していれば「雨季・乾季」がある気候(例:サバナ気候)、年間を通して降水量が安定していれば温帯や冷帯などと判断できるようになります。
まずは「見方」をマスターすることが、雨温図問題の第一歩。
次章では、実際に「熱帯・乾燥帯」の雨温図を使って、どんな特徴があるのかを読み解いていきましょう!
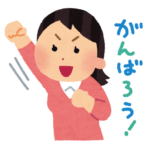
熱帯・乾燥帯の特徴と雨温図の見分け方
雨温図を使って世界の気候を見分けるうえで、まず押さえておきたいのが「熱帯」と「乾燥帯」です。どちらも暑い地域にあるという点では共通していますが、気温と降水量のパターンをしっかり読み取れば、区別は難しくありません。
熱帯は「高温多雨」か「雨季と乾季」で判断
気温が一年中高く、雨の量や時期で赤道近くの気候を判断しよう。熱帯には主に2つの気候があります。
年中高温多雨。気温が25℃前後でほとんど変化せず、降水量も毎月多く、雨季・乾季の差がないのが特徴。
→ 代表地:シンガポール、アマゾン川流域
こちらも高温だが、雨季と乾季がはっきりしている。雨季の月に降水量が急増し、乾季にはほとんど降らない。
→ 代表地:ナイロビ(ケニア)など
乾燥帯は「降水量が極端に少ない」のが決め手
棒グラフが非常に低く、年間を通して雨が少ないのが乾燥帯の特徴。乾燥帯には、次の2つがあります。
水量がほぼゼロ。気温は高いが、夜との寒暖差が激しい。雨温図では棒グラフがほとんどゼロに近い状態。
→ 代表地:カイロ、サウジアラビアのリヤドなど
砂漠よりはやや雨が多いが、それでも少なめ。年平均降水量は250~500mmほど。
→ 代表地:ウランバートル(モンゴル)など
雨温図の特徴をしっかり押さえることで、熱帯と乾燥帯の判別はぐっと簡単になります。
次章では、最も種類が多くて混乱しやすい「温帯」の雨温図をスッキリ整理していきましょう。

温帯の多様性—各気候区分と雨温図の特徴
温帯は、日本を含む地域が多く属しており、季節の変化がはっきりしているのが特徴です。ただし、温帯にもいくつかの区分があり、雨温図の読み取りで混乱しやすいポイントでもあります。ここでは、代表的な温帯の3つのタイプを比較しながら、見分けるコツを解説します。
温暖湿潤気候は「夏に雨が多く、冬に乾燥」
日本の本州などが代表。夏は蒸し暑く、冬は乾いた寒さが特徴。温暖湿潤気候は、日本の大部分が属する気候です。
-
夏は高温多湿で、降水量が多い(梅雨・台風)
-
冬は気温が下がるが、降水量は少なめ
雨温図では、気温が6〜8月に上昇し、棒グラフ(降水量)も同じ時期に高くなるのが特徴です。日本の雨温図が出たら、まずこのパターンを思い出しましょう。
西岸海洋性気候は「年間を通して安定」
イギリスやフランスなど、ヨーロッパ西部の典型的な気候。西岸海洋性気候は、年間を通じて温暖で、気温の変化が少なく、降水量も一年を通してほぼ一定なのが特徴です。
-
夏も冬も極端な気温になりにくい
-
季節風や偏西風の影響を受けにくい
雨温図では、折れ線グラフ(気温)がなだらかで、棒グラフが全体的に平均的な形になります。
地中海性気候は「夏に乾燥、冬に雨」
気候の逆転パターンに注意。夏と冬で雨の量が大きく変わる。地中海性気候は、名前の通り地中海沿岸に多い気候です。特徴は、夏に晴れて乾燥し、冬に雨が多くなるという逆のパターン。
-
気温は夏に高くなる
-
降水量は夏に少なく、冬に多い(珍しいタイプ)
雨温図では、高い気温に対して棒グラフが下がり、逆に気温が低い時期に棒グラフが上がるという形になります。
温帯の気候は似ているようでそれぞれ特徴が異なります。雨温図の形と、雨が多い季節に注目することが見分けのカギになります。
次章では、さらに気温が低くなる冷帯・寒帯の雨温図とその特徴を見ていきましょう!

冷帯・寒帯の気候特性と雨温図の読み解き方
冷帯と寒帯は、緯度が高く気温の低い地域に見られる気候です。どちらも寒さが特徴ですが、気温の下がり方や降水量の傾向に違いがあり、雨温図から判断することができます。ここでは、それぞれの気候区のポイントを押さえましょう。
冷帯は「夏と冬の差が大きい」
夏は短く暑く、冬は長くて極寒。大陸の内陸部に多い。冷帯は、ロシアのシベリアやカナダなどに見られ、冬の寒さが非常に厳しいのが特徴です。
-
夏は短くて暑い(20℃前後まで上がることも)
-
冬は氷点下20〜30℃にもなることがある
雨温図では、気温の折れ線が夏に一気に上がり、冬に急降下します。降水量は夏の方がやや多いパターンが多く、気温差が極端なグラフの形が特徴です。
寒帯は「一年中寒い」
夏も10℃未満。降水量も極端に少ない。寒帯は、北極・南極周辺の地域に見られる気候で、1年中気温が低く、植物もほとんど育たない地域です。
-
夏でも平均気温が10℃未満
-
一年中氷点下になることもある
雨温図では、折れ線グラフが常に0℃以下か、10℃に届かない水準になっています。降水量も非常に少なく、棒グラフは低いままです。
気温の「最高点」と「最低点」に注目!
冷帯と寒帯の見分けは、気温グラフの山の高さがカギ。両者の違いは夏に10℃を超えるかどうか。
-
10℃を超えれば「冷帯」
-
超えなければ「寒帯」
この1点に注目すれば、似たような雨温図でも簡単に区別できます。
寒い地域ほど、気温の変化が雨温図にはっきり表れます。
次章では、ここまで学んだ内容を活かして「雨温図から気候帯を見分けるコツ」やテストで使える勉強法をご紹介します。

雨温図を活用した世界の気候帯の判別法と学習のコツ
ここまで、雨温図をもとに世界の気候帯ごとの特徴を学んできました。テストや入試では「この雨温図はどの気候帯?」という問題がよく出題されます。この章では、実際に問題に答えるための見分け方と、効率的な学習法を紹介します。
「気温」と「降水量」のセットで判断する
気温だけ、降水量だけを見るのではなく、2つの組み合わせで気候帯を特定。まず大切なのは、気温と降水量を“セット”で考えることです。
-
一年中暑くて雨が多い → 熱帯雨林気候
-
暑いが雨が少ない → 乾燥帯
-
四季がはっきりしていて夏に雨 → 温暖湿潤気候
-
夏に乾燥して冬に雨 → 地中海性気候
-
気温差が大きく、夏だけ暑い → 冷帯
-
一年中寒い → 寒帯
このように、「いつ暑いのか?」「雨は多いのか?いつ降るのか?」という視点で見分けるのがコツです。
「季節」の流れから“半球”を判断する
気温の高い時期から、北半球か南半球かも見分けられる。テストでは、「この雨温図の地域は北半球か南半球か?」という設問もよく出ます。
-
6〜8月に気温が高い → 北半球
-
12〜2月に気温が高い → 南半球
この判断ができると、候補の地域を一気に絞ることができ、他の選択肢の誤りにも気づきやすくなります。
覚えるより“使いこなす”勉強法を
丸暗記ではなく、「見て考える」練習を繰り返そう。雨温図の学習では、グラフを見て、頭の中でイメージをつなげる練習が重要です。
-
「気温の山が高いな」→ 夏がある→季節の差がある気候
-
「雨が少ないな」→ 乾燥帯かも?
このように、「見て→考えて→分類する」ことで、記憶が定着しやすくなります。
プリントや問題集で、雨温図と地域・気候名をマッチングする練習を繰り返すのが、もっとも効果的な勉強法です。
まとめとして、記事全体のポイントと、勉強への活かし方をもう一度整理しておきましょう。
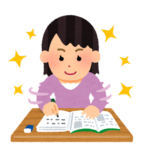

雨温図は、世界の気候を“視覚的”に理解できる便利なツールです。気温と降水量の変化をしっかり読み取れば、熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯の見分けがグッと楽になります。「見て→考えて→分類する」練習を重ねることで、テストの頻出問題にも自信をもって対応できるようになるはずです。
ぜひ本記事の内容を活かして、地理の苦手克服や得点アップにつなげてください!
お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 6,697人 に閲覧されています。
.jpg)