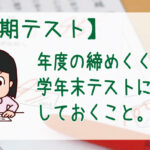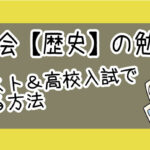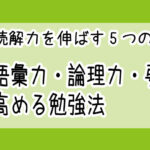飛鳥時代を総整理!定期テストと入試に効く6つの重要ポイント
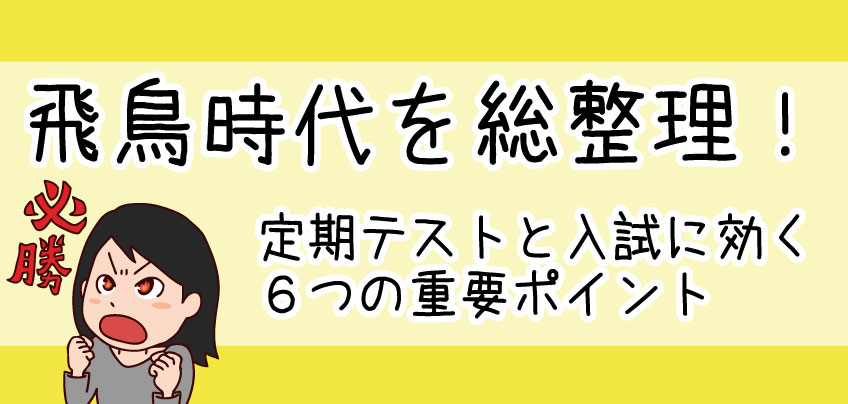
目次
飛鳥時代、得点アップのカギを握る!
中学社会の歴史分野で、意外と苦手とする生徒が多いのが「飛鳥時代」。聖徳太子、大化の改新、律令制度…登場人物や制度名が多く、何がどう変わったのか整理しきれず、テストでも混乱してしまうことがよくあります。しかし、飛鳥時代はその後の奈良・平安時代にもつながる「古代日本の土台」となる重要な時代です。
この時代のポイントをしっかりおさえておけば、定期テストはもちろん、高校入試でも確実な得点源になります。さらに、政治・文化・外交とさまざまな面で改革が進んだ飛鳥時代は、理解を深めることで社会全体の流れを読み解く力も身につきます。
定期テストや入試対策に直結する「飛鳥時代の6つの重要ポイント」をテーマに、時代の背景から人物、制度の意義までわかりやすく解説します。各章ごとに要点を整理しながら、混同しがちなキーワードの違いや、テストで狙われやすいポイントも紹介。読むだけで自然と頭に入る構成で、効率よく学習を進められます。
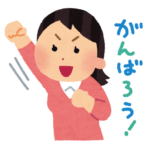
飛鳥時代の基礎から応用まで、この1本でしっかりおさらいしましょう!
第1章:飛鳥時代の始まりと蘇我氏の台頭
飛鳥時代の幕開けを見極めよう
蘇我氏が握った政権の実権
飛鳥地方に都が置かれた6世紀後半、日本は豪族が政治の主導権を争う時代にありました。その中で台頭したのが仏教受容を進めた「蘇我氏」です。渡来人との関係を利用し、仏教という新たな文化を取り入れた蘇我氏は、他の豪族より一歩先を行く存在となりました。
特に注目すべきは、蘇我馬子が崇峻天皇を暗殺し、推古天皇を即位させた点です。これは、蘇我氏の権力集中を示す事件であり、以後の政局に大きな影響を与えました。さらに、推古天皇のもとで摂政となった聖徳太子の存在が、政治改革への足がかりをつくることになります。
聖徳太子の登場と改革の兆し
聖徳太子は、飛鳥時代において最も重要な人物の一人です。彼はまだ幼い推古天皇の政治を支える摂政として活躍し、「冠位十二階」や「十七条の憲法」などの改革の基盤を構築していきます。
一方、蘇我氏の権力は絶対的で、他の豪族たちの反感も強まっていました。こうした背景が、後の大化の改新へとつながっていくのです。
飛鳥時代のスタートには、蘇我氏の存在が不可欠でした。仏教の受け入れ、崇峻天皇の排除、推古天皇の擁立、そして聖徳太子の登場という一連の流れは、歴史の大きな転換点です。テストでは「人物と出来事の関係」「仏教の導入と政治の変化」に注目しておくとよいでしょう。
第2章:聖徳太子と政治改革のはじまり
改革の先駆け、聖徳太子の挑戦
冠位十二階の制度化とその目的
603年、聖徳太子は「冠位十二階」という官位制度を導入しました。これは才能や功績に応じて役職を与える制度で、それまでの氏姓制度に基づく世襲的な官僚制度に大きな風穴を開けるものでした。身分に関係なく能力重視で官職を与えるこの制度は、中央集権国家を目指すうえで非常に画期的でした。
また、冠位の名称に「徳・仁・礼・信・義・智」などの儒教的価値観を反映させていたことから、中国文化への敬意とその受容も読み取れます。
十七条の憲法に込められた思想
翌604年、聖徳太子は「十七条の憲法」を制定しました。これは現在の憲法とは異なり、官人に対する道徳的・精神的な指針を示したものであり、特に「和をもって貴しとなし」とする第一条が有名です。
十七条の憲法は、中央集権的な国家運営を推進するうえでの統治理念を確立する役割を果たしました。この憲法により、天皇を中心とした国家体制の構築が目指され、後の律令制度にも影響を与えることになります。
外交と仏教文化の発展
聖徳太子は国内改革と並行して、対外政策にも積極的でした。特に注目すべきは、607年に遣隋使を派遣したことです。このときの国書には「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と記されており、中国(隋)に対して対等な外交姿勢を示しました。
また、仏教を厚く信仰していた聖徳太子は、法隆寺などの建立を進め、仏教を国の柱とする体制を整えました。こうした文化政策は、飛鳥文化の形成に大きく寄与しています。
聖徳太子の改革は、氏族による支配から天皇中心の中央集権国家への第一歩でした。冠位十二階や十七条の憲法、そして対等外交と仏教の保護など、そのすべてが後の日本の国家制度に大きな影響を与えました。定期テストでは「制度の目的」「中国との関係」「仏教との関わり」などを整理しておくと効果的です。
第3章:大化の改新と律令国家への道
蘇我氏の専横と改革の必要性
乙巳の変と蘇我氏の滅亡
645年、中大兄皇子と中臣鎌足は、宮中で蘇我入鹿を暗殺する「乙巳の変(いっしのへん)」を実行します。この事件によって蘇我氏の権勢は終焉を迎え、皇族主導による政治改革の道が開かれました。
このクーデターは、日本史上でもまれに見る大きな転換点であり、天皇中心の国家運営が実現に向かって動き出すきっかけとなりました。
大化の改新とその四つの改革
乙巳の変を経て始まった「大化の改新」では、国家の統治機構を整えるために以下のような改革が実行されました。
- 公地公民制:土地と人民を国家のものとし、支配者層の私有を禁じる制度。
- 班田収授法:国が一定の土地を人民に分け与え、収穫に応じた税を納めさせる。
- 戸籍と計帳の整備:人口や財産を把握するため、全国的に台帳を作成。
- 地方行政制度の整備:国・郡・里といった地方制度を整備し、中央から派遣された役人によって統治。
これらの改革は、中国(唐)の制度を手本にしたもので、日本が中央集権国家へと進化するための基盤となりました。
天皇中心の律令国家へ
大化の改新以降、日本では「律令国家」への整備が進められました。律とは刑法、令とは行政法を指し、これらを組み合わせた「律令制度」によって国家を運営しようというものです。
この改革により、天皇の権威が強化され、貴族たちは律令に従って役職に就く仕組みが整えられました。天皇を頂点とした法治国家が形成され、後の奈良時代の平城京や正倉院の建設へとつながっていきます。
大化の改新は、単なる政治的な事件ではなく、日本の国家構造そのものを変える一大プロジェクトでした。中大兄皇子らの意志と行動によって、氏族による支配から、法と制度に基づいた国家運営へと大きく舵が切られたのです。テストでは、「改革の内容」「制度の目的」「中国との関係性」などを押さえておくことが得点アップの鍵となります。
第4章:天武・持統天皇と律令体制の確立
皇位継承争いから生まれた新たな国家運営
壬申の乱と天武天皇の即位
672年、天智天皇の死後、その跡継ぎを巡って「壬申の乱(じんしんのらん)」が起こります。これは日本最大級の内乱であり、天智天皇の弟・大海人皇子とその子・大友皇子の間で激しい争いが繰り広げられました。
勝利した大海人皇子は天武天皇として即位し、皇族による強力な中央集権体制の確立に着手します。天武天皇は、天皇を中心とする国家を築くため、政治・軍事・宗教にわたるさまざまな制度改革を断行しました。
持統天皇と律令国家の整備
天武天皇の死後、皇后であった持統天皇が即位します。彼女は天皇として政治を主導し、天武天皇の遺志を受け継いで律令制度の完成を目指しました。
特に注目すべきは以下の3つの施策です:
- 藤原京の建設:日本初の本格的な都城制に基づく都。唐の長安をモデルとした碁盤目状の都市計画が特徴。
- 戸籍制度の整備:飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)を制定し、人民の管理を厳格に行う。
- 律令の編纂準備:後の「大宝律令」完成に向け、法整備の下地を作った。
持統天皇は、女性でありながら非常に実務的な政策を進め、国家の制度面を大きく発展させたことで知られています。
律令国家体制の構築と影響
天武・持統天皇の時代は、日本が氏族社会から脱却し、「法」によって国を治める国家へと変貌を遂げる重要な転換期です。彼らの取り組みによって、天皇を中心に全国を統治する律令国家体制が着実に整っていきました。
これは後の奈良時代に成立する「大宝律令」(701年)につながり、そこから平安時代初期まで律令による統治が続きます。天武・持統両天皇の功績は、まさに日本の政治の骨組みを作ったと言っても過言ではありません。
天武・持統天皇の時代は、律令国家成立への基盤が形作られた歴史のターニングポイントです。彼らは単なる皇族ではなく、明確なビジョンを持って国家の未来を設計した改革者でもありました。定期テストでは、「壬申の乱」「藤原京」「律令制度」といったキーワードを正確に押さえることが、得点アップにつながります。
第5章:大宝律令とその仕組み
律令国家の完成を告げる大改革
大宝律令とは何か?
大宝律令は、文武天皇の時代に唐の律令制度をモデルにして作られた日本最初の本格的な律令法典です。藤原不比等(ふひと)と刑部親王(おさかべしんのう)によって編纂されました。
- 「律」は刑罰に関する規定(刑法)
- 「令」は行政や人々の生活に関する規定(行政法・民法)
この2つを合わせた法体系が、「律令制度」と呼ばれます。
中央政府の構造と役割
大宝律令では、国家運営の仕組みが明確に定められました。特に注目すべきは、政府の機構と役職制度です。
- 太政官(だいじょうかん):国家の最高機関。政務全般を司る。
- 神祇官(じんぎかん):神々への祭祀を担当。
- 国司・郡司(こくし・ぐんじ):地方の行政官。中央から派遣され、地方統治を行う。
また、全国を「国・郡・里(こく・ぐん・り)」の三段階に区分し、戸籍・税・労働が管理されました。
民衆の生活と律令制度
大宝律令は庶民の暮らしにも大きな影響を与えました。特に、以下のような制度が注目されます。
- 班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう):6歳以上の男女に土地を支給し、一定期間後に返還させる制度。土地の公平な配分と租税徴収を目的とする。
- 租・庸・調(そ・よう・ちょう):農民が納める税の種類。
- → 租:田からとれる米
- → 庸:労働力や布など
- → 調:特産物(絹、綿など)
このように、大宝律令は国民一人ひとりにまで関わる法律として、全国に行き渡る制度でした。
大宝律令は、日本が法によって統治される「法治国家」へと変化する第一歩を象徴するものでした。天皇を頂点とし、法律と制度で全国を統治する体制は、その後の奈良時代、平安時代にも大きな影響を与え続けます。
定期テストでは「大宝律令」「藤原不比等」「班田収授法」「租庸調」といった用語の意味を正確に理解し、しくみを図や表で整理すると、得点に直結します。
第6章:テストに出る!
飛鳥時代の重要キーワード総復習
飛鳥時代の人物編
飛鳥時代には多くの重要人物が登場します。それぞれの功績や関係性を押さえておきましょう。
- 聖徳太子:推古天皇の摂政。冠位十二階、十七条の憲法、小野妹子を遣隋使として派遣。
- 蘇我馬子:仏教の受容を進めた。物部氏を倒し、政治の実権を握る。
- 中大兄皇子(のちの天智天皇):大化の改新を推進。中臣鎌足と協力し蘇我氏を倒す。
- 中臣鎌足:のちの藤原鎌足。藤原氏の祖。大化の改新の中心人物。
- 天武天皇・持統天皇:律令国家の土台を築く。
人物の系図や政治的なつながりを図解で整理すると、理解が深まります。
制度・政治・外交編
飛鳥時代の政治制度や外国との関係も出題されやすいポイントです。
- 冠位十二階(603年):才能や功績に応じて役職を与える制度。
- 十七条の憲法(604年):役人としての心構えを示したルール集。
- 遣隋使の派遣(607年):中国との交流を強め、国際的な認知を目指した。
- 大化の改新(645年):蘇我氏を倒し、天皇中心の国家づくりを始める。
- 班田収授法・租庸調:農民に土地を支給し、税制度を整えた。
これらの年号や名称は選択肢や並べ替え問題で頻出なので、語呂合わせや図表で覚えておきましょう。
文化・宗教・建築編
飛鳥時代は日本文化の形成期としても重要です。仏教の伝来や寺院建築も頻出事項です。
- 仏教の伝来(538年 or 552年):百済から仏像や経典が伝えられた。
- 法隆寺:聖徳太子が建立した世界最古の木造建築。
- 飛鳥文化:仏教を中心とした国際色豊かな文化。
- 白鳳文化:天武天皇〜持統天皇の時代に花開いた文化。
仏像や建物の特徴も、資料問題として出題されることがあるので、写真や図と一緒に覚えましょう。
飛鳥時代は政治制度・宗教・文化と、さまざまなテーマが凝縮された学習単元です。出題パターンも比較的決まっているため、重要語句を中心に整理すれば、大きな得点源になります。ノートや単語カードにまとめる、声に出して復習するなど、自分なりのやり方でしっかり覚えましょう。
飛鳥時代を攻略すれば、歴史がもっと得意になる!
飛鳥時代は、日本が本格的な国家体制を築き始めた、歴史上の大きな転換点です。聖徳太子による政治改革から始まり、大化の改新、律令制度の確立へと続くこの時代には、覚えるべき重要な出来事・人物・制度が数多くあります。一見すると複雑に思えるかもしれませんが、今回のコラムで紹介した6つの視点から丁寧に学べば、流れがスッキリと見えてきます。
暗記に頼るだけでなく、「なぜそうなったのか」「どのように変化したのか」といった“因果関係”を意識して学ぶことが大切です。語呂合わせや図解、表にまとめるなど、自分に合ったやり方を取り入れてみましょう。

飛鳥時代を得意にできれば、奈良時代・平安時代といった次の単元への理解も深まり、歴史全体がもっと楽しくなります。歴史はストーリーです。一つ一つの出来事の背景を知ることで、点と点が線につながり、学びがぐっと身近になります。
さあ、今日から本格的に飛鳥時代マスターへの一歩を踏み出しましょう!
お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 1,040人 に閲覧されています。
.jpg)