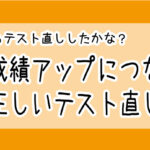現代文の読解力を伸ばす5つのステップ 語彙力・論理力・要約力を高める勉強法
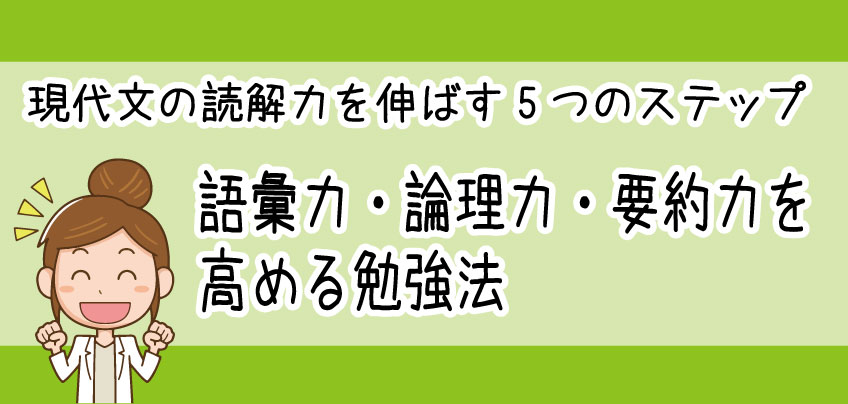

「現代文はなんとなく苦手…」そんな悩みを抱えていませんか?
現代文の読解力は、ただ文章を読むだけではなかなか身につきません。「筆者の言いたいことがわからない」「選択肢の違いが見抜けない」「記述がうまく書けない」――こうした悩みは、多くの中高生が直面するものです。
しかし、現代文は「感覚で読む教科」ではありません。論理的に読み進めるコツを知り、段階的に練習することで、誰でも確実に読解力を伸ばすことができます。
目次
現代文読解の基本とは?—感覚ではなく論理で読む
感覚読解と論理読解の違い
現代文で多くの生徒がつまずく理由の一つが、「感覚で読んでしまう」ことです。「なんとなくこういう意味かな?」と、直感や語感に頼って答えを選んでしまうと、記述式や選択式の問題で正解率が下がります。
一方で、論理読解とは、文章の構成や筆者の主張、段落ごとの役割などを分析しながら、「何が根拠か」「どこに答えのヒントがあるか」を冷静に探す読み方です。現代文は「国語の中の理数科目」とも言われるほど、論理的思考力が求められる教科なのです。
段落構成と指示語の役割に注目
論理的に読むためには、まず「段落構成」を意識することが大切です。文章はたいてい「導入→主張→理由→具体例→結論」という形で展開されています。各段落にどんな役割があるかを考えながら読むことで、筆者の論理展開を見抜く力がついてきます。
また、「それ」「このこと」「しかし」などの指示語や接続語にも注意を払いましょう。指示語は、直前や前の段落の内容を受けており、設問で「〜とは何を指しているか」と問われることが非常に多いです。これを的確に読み取れるようになると、正答率が格段に上がります。
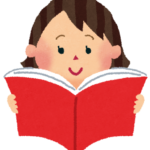
論理読解の力を身につけるには、
「なぜそう言えるのか?」
「どの文がその根拠か?」を
常に意識して読む姿勢が必要です。
次章では、その土台となる「語彙力」について詳しく掘り下げていきます。
語彙力を強化する—読解の土台を築く
語彙力は読解力の“足場”
現代文を正確に読み解くためには、語彙力が不可欠です。語彙力とは、「言葉の意味を正しく理解し、文脈に応じて使い分ける力」のこと。たとえば「抽象的」「相対的」「矛盾」などの語の意味が曖昧なままでは、筆者の主張を読み取ることも困難になります。実際、難解に感じる現代文の多くは、文章の難しさではなく語句の理解不足によって難しく感じているケースがほとんどです。知らない言葉が多ければ、その文全体の意味もぼやけてしまいます。語彙力は「文章を読む前提の力」。つまり、語彙がないと土台が崩れ、読解の積み上げができなくなるのです。
語彙を「覚える」から「使える」へ
語彙力を身につける際、ただ単語の意味を暗記するだけでは不十分です。重要なのは、「文脈の中で意味を理解し、自分の言葉で言い換えられるようにする」ことです。たとえば「矛盾」という言葉を覚えたら、「Aと言っていたのに、Bでは反対のことを言っている。これは矛盾している」といったように、例文を通じて使い方を確認しましょう。
また、読書や新聞、論説文の精読などを通して、日常的に新しい語彙に触れる機会を増やすことも効果的です。意味があやふやな語句が出てきたら、都度辞書を引く習慣をつけると、理解のスピードも上がっていきます。
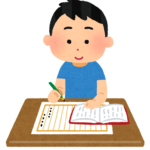
語彙力を高めることは、
すべての教科における
“読解の基礎体力”をつけることと同じです。
次章では、この語彙力を活かして
文章を論理的に読み進める「論理的思考力」について掘り下げていきます。
論理的思考を鍛える—演繹法と帰納法の活用
演繹法と帰納法を使いこなす
現代文の文章構成には、筆者の主張や論理展開が必ず存在します。そこで重要になるのが、「演繹法」と「帰納法」という論理の型です。
・演繹法は、「一般的な前提」から「具体的な結論」を導く方法。たとえば、「すべての人間は死ぬ。ソクラテスは人間。ゆえにソクラテスは死ぬ」といった形式です。
・帰納法は、「複数の具体例」から「共通点や結論」を導き出す考え方です。
現代文では、「この段落は具体例から始まっているから、これは帰納法のパターンだな」といった視点で読むと、筆者の論理展開がより明確に見えるようになります。
主張と根拠の関係を見抜く
論理的に読むうえで最も重要なのは、「主張」と「根拠」の関係を正しく把握することです。現代文では、筆者が「〜であるべきだ」「〜ということが言える」と主張する場面がありますが、その主張を支えているのが、前の段落や文中に示された“根拠”です。
設問で「筆者の主張はどれか?」「理由を選べ」などと問われたときは、必ず「その意見の背景にどんな理由があるか?」をセットで探す必要があります。このとき、接続語(たとえば「しかし」「なぜなら」「つまり」など)にも注目すると、論理の流れがつかみやすくなります。“主張→根拠→具体例”という構造を意識するだけで、文章全体がクリアに見えてくるのです。

論理構造を読み解く力がつくと、
現代文の文章が
「わかりやすく、筋の通ったもの」に見えてきます。
次章では、この論理的な読解を要約という形で
アウトプットする方法について解説します。
要約力を高める—文章の本質を捉える技術
要約は「読む力」と「伝える力」の融合
現代文の要約は、単なる文の短縮ではありません。筆者の主張や論点を正しく把握し、それを第三者にも伝わる形で簡潔に表現する力が求められます。
つまり、要約には「読む力(理解力)」と「書く力(表現力)」の両方が必要なのです。この力は、定期テストや入試だけでなく、社会に出てからも文章や会話を整理して伝える力として重宝されます。現代文の要約を学ぶことは、「思考と言語の整理整頓」をする訓練でもあるのです。
大事なのは「要点を見抜く力」
要約で最も重要なのは、「何が本文の中心となる主張なのか」を見抜く力です。文章全体を読んだあとに、「この文章は何が言いたいのか?」と自分に問いかけてみましょう。
-
筆者が最も強調している一文(たいていは結論や冒頭に近い文)
-
複数の段落をつなぐ“共通するキーワード”
-
「つまり」「したがって」など結論を導く接続語の後にある文
こうした要素を拾い上げて、「筆者の主張」と「その理由や背景」を中心にまとめると、質の高い要約ができます。
「削る」ではなく「再構成する」意識
多くの生徒が要約を苦手に感じる理由は、「文章を削って短くすればいい」と誤解しているからです。確かに、情報を削ることは必要ですが、単に文を短くするのではなく、要点を新たな形で再構成するという視点が大切です。要約では、語尾や文体の変更、接続の仕方など、自分の言葉でまとめ直す柔軟性も求められます。練習としては、「100字要約」や「1文で言い表す練習」を重ねることで、自然とまとめる力がついてきます。

要約力は、現代文の理解を“言語化”するための力です。
「自分で消化して、再び形にする」経験を積み重ねていくことで、
より深い読解力が身についていきます。
次章では、こうして培った力を本番で活かすための
「問題演習と復習法」について解説します。
実践的な読解演習—問題演習と解説の活用
まずは「量より質」の演習を意識しよう
現代文読解力を高めるには、問題演習が欠かせません。ただし、むやみにたくさん解くだけでは効果は薄く、一問一問を丁寧に取り組む“質重視”の学習が大切です。問題を解いたら、答え合わせをする前に「自分はなぜこの選択肢を選んだか」「筆者の主張はどこだったか」を振り返る時間を持ちましょう。これは「答え合わせで正誤を確認する」だけでは得られない、思考の過程を見直す訓練になります。間違えた問題も、深く掘り下げることで自分の理解不足を見つける貴重な機会になります。
解説の「読み込み」が力になる
多くの生徒が見落としがちなのが、「解説をしっかり読む」ことの大切さです。模範解答や選択肢の解説文には、なぜその選択肢が正解で、なぜ他が誤りなのかという論理的な根拠が明確に示されています。特に難問では、自分の考えとのズレを客観的に修正するきっかけになります。解説の中に出てくるキーワードや構造、筆者の意図などを読み取ることで、現代文の文章に対する「読み方の型」が身についてくるのです。問題集や過去問では、解説までじっくり読み込むことが、読解力のレベルアップに直結します。
「得点力」を意識した演習の進め方
入試や定期テストでは、単に理解できるだけでなく、「得点につなげる力」が求められます。そのためには、問題形式ごとの対策が必要です。
-
選択問題 →「根拠の文」と選択肢の一致を精査
-
記述問題 →「抜き出し」「要約」「言い換え」など出題意図を見抜く
-
誤文訂正 →「文脈」と「論理性」のチェック力を高める
特に記述問題では、「どこまで書くか」「どう書き始めるか」といった型のトレーニングをしておくと安心です。

問題演習は、理解した知識や読解技術を
「実践の場で活かす」ための訓練です。
演習を通じて、自分の弱点を知り、
そこを少しずつ修正することで、
現代文は必ず得意分野に変わっていきます。
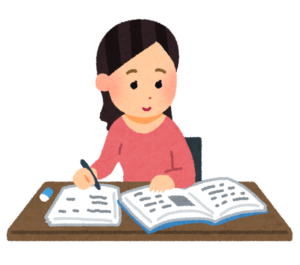
現代文の読解力は、一朝一夕で身につくものではありません。ですが、「論理的に読む」「語彙を深める」「要点をつかむ」――こうした力を少しずつ育てていくことで、確実に“読める感覚”が身についてきます。
重要なのは、「なんとなく読む」から「理由を持って読む」へと意識を変えること。
問題を解いたあとも、自分の読み方や考え方を丁寧に振り返ることで、読解力は着実に伸びていきます。「読めた!」「わかった!」という小さな成功体験の積み重ねが、やがて入試や実力テストでの大きな成果につながります。
このコラムを参考に、現代文への苦手意識を少しずつ自信へと変えていきましょう。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。
当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。
まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 844人 に閲覧されています。
.jpg)