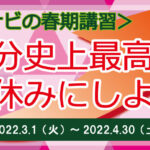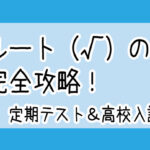中学生の作文対策完全ガイド:定期テスト・大阪府入試に対応する書き方と勉強法
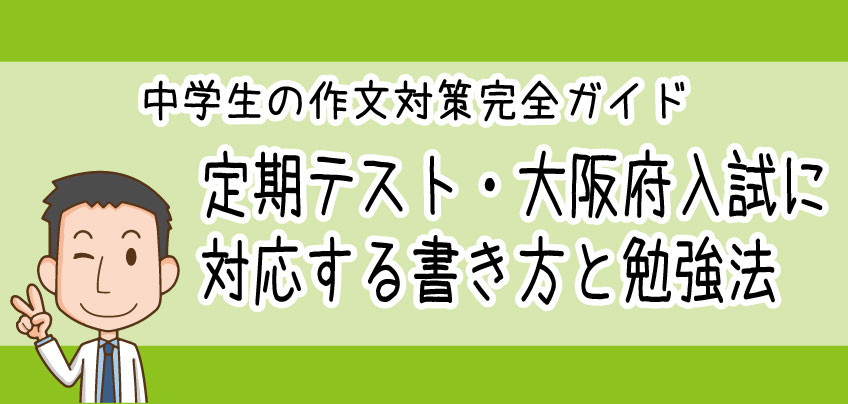
「作文って何を書けばいいのか分からない」
「時間内に書き終わらない」
ー そんな声をよく耳にします。 ー

国語の中でも“自由度が高くて正解が見えにくい”作文は、多くの中学生にとって難関です。
特に大阪府の公立高校入試では作文が必出。内容の質だけでなく、構成や表現の工夫、時間配分まで含めて完成度が問われます。でも、作文には「型」があります。正しい構成と書き方を身につければ、誰でも安定した得点が取れるようになります。
この記事では、作文の基本から具体的な書き方、入試対策、自己添削のコツ、日常での練習法までを5章構成で解説。

第1章:作文の基本構成を理解しよう
― 起承転結と三段構成のポイント ー
「起承転結」で話の流れをつかむ
「起承転結(きしょうてんけつ)」は、文章の基本的な展開方法です。
- 起:話の導入(テーマに対する問題提起や状況説明)
- 承:話を広げる(具体的な事例や背景)
- 転:話の転換点(自分の考えや立場の提示)
- 結:まとめ(結論と読後感を意識した締め)
この型はストーリー性を持たせたい場合や、自分の経験を書く場面に向いています。
論理的に書きたいなら「三段構成」がおすすめ
特にテストや入試でよく使われるのがこの「三段構成」です。
- 序論(導入):テーマに対する自分の立場や主張を述べる
- 本論(理由・具体例):主張の根拠となる理由や経験を述べる
- 結論:全体をまとめて再度自分の考えを伝える
<例>
「私が考える理想のリーダー像」→
- 序論:「私は“相手の話をよく聞くリーダー”が理想だと思います。」
- 本論:「中学の部活で、キャプテンがメンバーの意見を受け止めてくれたことで、全体の雰囲気が良くなりました。」
- 結論:「この経験から、聞く力のあるリーダーこそ信頼されると感じました。」
論理的に読みやすく、評価基準にも合致しやすいため、入試では特に有効です。
作文の構成が決まっていると、「何を書くか」が明確になり、時間配分もしやすくなります。

ハカセ
第2章:具体例の使い方とテーマの読み取り方
― 説得力ある文章の書き方 ー
抽象的な意見だけでは弱い!
作文でよくある失敗例が、「私は友情が大切だと思います」などの抽象的な意見だけで終わってしまうことです。読み手にとっては「なぜそう思うの?」「具体的には?」という疑問が残り、説得力が弱まります。
- →【NG例】「努力は大切だと思います。なぜなら頑張ることは良いことだからです。」
- →【OK例】「私は努力が大切だと思います。中学の体育祭でリレー選手に選ばれ、毎朝早起きして練習した結果、本番で自己ベストを出せたからです。」
このように、自分の経験や周囲の出来事を根拠として書くことで、読み手を納得させる力が生まれます。
テーマを「ズレずに」読み取る方法
作文では、テーマを外さないことが重要です。例えば「学校生活で学んだこと」というテーマで、「家族の大切さ」ばかり書いてしまうと減点対象になります。
【ポイント】
テーマに含まれる「キーワード」に注目し、「その言葉にしっかり答える」こと。
<例>
「自分を成長させた経験」→「○○大会での失敗を乗り越えた話」など、“成長”というキーワードに明確に応える内容にする。
具体例を書くときは「5W1H」を意識!
Who(誰が)What(何を)When(いつ)Where(どこで)Why(なぜ)How(どのように)を意識して具体的に書くと、内容がぐっと引き締まります。
- NG例:「部活で頑張りました。」
- OK例:「中学2年の秋、吹奏楽部の定期演奏会でソロパートを任され、毎日1時間練習を重ねました。」
作文は「思っていること」よりも、「伝わること」が評価されます。

ハカセ
第3章:大阪府公立高校入試の出題傾向と対策
ー 入試の作文問題を徹底分析 ー
出題形式の特徴を押さえよう
大阪府の作文問題の特徴は、以下のような構成です。
- 制限字数:おおむね100〜200字(年度により異なる)
- テーマ:受験生自身の体験や考えを問うものが多い
- 文末指定:「〜と私は考える」「〜について述べよ」などが定番
【過去出題例】
- 「周囲の人と協力して成し遂げた経験について書きなさい」
- 「身近なことで、社会と関わる経験について述べなさい」
テーマは一見シンプルですが、論理的な構成と具体的な事例がないと高得点は望めません。
高得点者が意識しているポイント
大阪の入試作文では、次のような点が重視されます。
- 内容がテーマに合っているか(ズレていないか)
- 主張と理由が論理的につながっているか
- 自分の体験や意見が具体的に書かれているか
- 誤字脱字がなく、文法的に正しいか
【ポイント】「何を伝えたいか」が明確であることが最も重要です。
模範解答を読み比べると、主張と具体例がセットになっていることが共通点です。
本番で焦らないための練習法
作文の完成には、思考・構成・記述の3ステップが必要です。時間制限がある入試では、「時間内に書ききる練習」が必須。
【おすすめ練習法】
- 過去問や想定テーマを使って構成メモを5分で書く
- 制限時間(15分〜20分)で本文を書く
- 書いた後に自分で添削 or 家族や先生に見てもらう
この繰り返しで、本番でも落ち着いて書ける力がついていきます。
入試作文は“慣れ”が大きな武器になります。

ハカセ
第4章:書いた後が勝負!
ー 自己添削と第三者のアドバイス活用術 ー
自己添削は3つの視点でチェック!
「構成」「内容」「表現」の3つを見直すことで、文章の完成度が一気に上がる。
【1】構成の確認:
- 起承転結や三段構成になっているか?
- 主張と具体例が論理的につながっているか?
【2】内容の確認:
- テーマからズレていないか?
- 主語と述語の関係はおかしくないか?
- 説得力のあるエピソードが書けているか?
【3】表現の確認:
- 文法・漢字・助詞の使い方に間違いはないか?
- 同じ言葉の繰り返しが多くなっていないか?
【ポイント】「声に出して読む」とミスに気づきやすくなります。
「第三者の目」を借りると視野が広がる
自分では気づけない弱点を知るには、他人の意見が有効。
- 家族や友人、先生に読んでもらう
- 「伝わりやすいか?」「印象に残るか?」を聞く
- 指摘された点を次回の作文に活かす
→【実践例】「自分では“いい話”だと思っていたが、先生に“エピソードが抽象的すぎる”と指摘された。次はもっと具体的に書くように意識した。」
第三者からのフィードバックを受け入れることで、作文に“読み手目線”が加わり、表現が磨かれていきます。
「比較」で成長を実感する
自分の作文を時系列で比べることで、成長と課題が見えてくる。
- 1か月前と今の作文を読み比べる
- 同じテーマで2回書いてみる
- 先生に添削された後の変化を見る
→ 書きっぱなしにせず、自分の成長を「見える化」することがモチベーションにもつながります。

ハカセ
第5章:毎日の習慣で差がつく!
ー 作文力を高めるトレーニング法 ー
「1日3行」日記で文章の筋トレ!
短くても毎日書くことが作文力アップへの第一歩。
<例>
- 今日は委員会の話し合いで意見が対立した。
- でも、自分の考えを伝えることで理解してもらえた。
- 伝えることの大切さを実感した。
→このように、出来事→考え→気づきをセットにして書く習慣をつけましょう。構成力が自然と身につきます。
ニュースや読書から「書くネタ」をストック
身近な話題にアンテナを張っておくと、作文の内容に深みが出る。
- ニュースを見て、「自分ならどう思うか?」を考える
- 本を読んだら感想ではなく「自分の経験とどうつながるか」を書く
- 家族との会話、学校での出来事など、日常に“作文ネタ”はたくさんある
→「材料不足で書けない」を防ぐためにも、ネタの引き出しを増やす努力をしておきましょう。
「決まった型」で練習すると上達が早い
毎回同じ構成で書くことで、自動的に構成力が鍛えられる。
おすすめは三段構成のテンプレート
- 【序論】私は〇〇だと思います。
- 【本論】なぜなら〜という経験があるからです。
- 【結論】この経験から、私は〜と考えるようになりました。
→この型に合わせていろんなテーマで作文を書いてみましょう。型を覚えることで、時間がなくても自然に書けるようになります。
日々の生活の中で「少し書く習慣」をつけるだけで、作文は確実に上達します。
“うまく書こう”よりも、“書き続けよう”の意識で、入試本番でも迷わず書ける自分を作っていきましょう。
作文は、「センス」や「文章が得意かどうか」ではなく、正しい構成と表現の練習を積めば誰でも伸ばせるスキルです。特に大阪府の公立高校入試では作文が必出であり、ここで差がつくケースも少なくありません。

ハカセ
お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 661人 に閲覧されています。
.jpg)