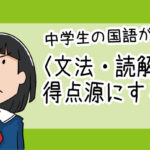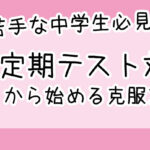読解力アップで国語が得意に!定期テスト&入試を制する勉強法
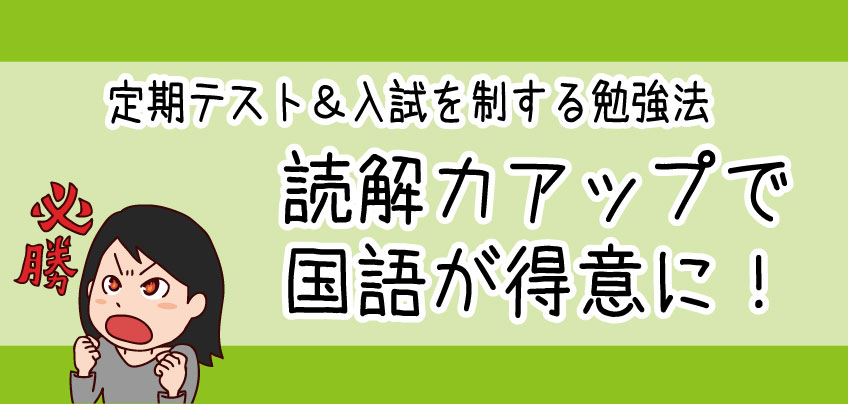
読解力がないと国語は伸びない?本当の「読み方」の力とは
「本文の意味がなんとなくしか分からない」

国語のテストや入試で点数が伸び悩んでいる生徒の多くが抱える共通の課題、それが“読解力”です。
読解力とは単に「本を読む力」ではありません。文章の構造を理解し、筆者の意見や主張を正確に捉え、設問に沿って適切に答えるための“情報処理の技術”なのです。この力が不足していると、どれだけ真面目に本文を読んでも「なんとなく」で解答してしまい、結果的に点が取れない…という事態になりがちです。
さらに、読解力の不足は国語だけでなく、英語の長文、理科や社会の資料読み取り、さらには数学の文章題にまで影響を与えます。つまり、読解力はすべての教科に関わる“学力の土台”なのです。
本コラムでは、読解が苦手な中学生・高校生のために、
- ・読解力不足の原因と対策
- ・読み方の基本ステップ
- ・問題形式ごとのコツ
- ・語彙・文脈力の鍛え方
- ・本番に強くなるための演習法
を5つの章に分けて詳しく解説していきます。
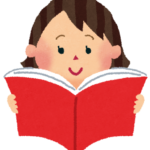
“なんとなく読む”を卒業して、
“論理的に読む”力を身につけ、
国語を得意科目に変えていきましょう!
第1章:なぜ読めない?
読解力が伸びない原因とその正体
「本文はちゃんと読んだのに、なぜか点が取れない」
「問題の意味がよくわからない」
このように、読解問題に苦手意識を持つ生徒は少なくありません。実は、その原因の多くは“読み方の技術”が身についていないことにあります。
原因①:「何を読めばいいのか」がわかっていない
国語の読解問題は、「ただ本文を読む」だけでは不十分です。
特にテストや入試では、限られた時間の中で、設問に答えるために必要な情報をピンポイントで読み取る力が求められます。
→ どこに注目すべきか、何を探しながら読むべきかが分からないままでは、正解にはたどりつけません。
原因②:語彙・文法の基礎力不足
文章の理解には、語彙力(言葉の意味)や文法理解が欠かせません。
知らない単語が多かったり、長文を一文ずつ正確に読み取れなかったりすると、文章全体の意味も曖昧になってしまいます。
【例】
「皮肉」「逆説」「主張」「対比」などのキーワードを知らなければ、筆者の意図を見抜くのは困難です。
原因③:設問の意図が読み取れない
本文がある程度読めても、設問の意図を取り違えてしまうケースも少なくありません。
【例】
「理由を答えなさい」とあるのに、「筆者の意見」を答えてしまう
「抜き出しなさい」を読まず、自分の言葉で書いてしまう
→ これは“読解力の欠如”というよりも、設問の読み飛ばし・読み間違いが原因です。
原因④:「論理的な読み方」ができていない
読解には“ルール”があります。
たとえば、接続語の役割、段落ごとの構成、主張と根拠の関係など、文章には論理的な構造が必ず存在します。
→ この構造を意識せずに「なんとなく」読んでしまうと、筆者の意図や設問の答えが見えにくくなってしまいます。
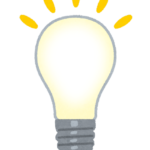
読解力が伸びない理由は、「ちゃんと読んでいるつもり」でも、“読み方の技術”が身についていないことにあります。特に、「何を」「どのように」読むのかがあいまいなままでは、正確な読み取りはできません。
第2章:読み方の型を身につける!
読解力を伸ばすための基本ステップ
そのため、正しい“読み方の型”を身につければ、誰でも確実に伸ばすことができます。
この章では、文章を読むときに意識すべき基本の読み取りステップを紹介します。
ステップ①:「設問」を先に読む
国語の問題では、本文を読む前に設問を先に確認するのが鉄則です。
なぜなら、どんな情報を探しながら読むべきかが明確になるからです。
【ポイント】
- 「傍線部の理由を聞いている」なら、因果関係を探す
- 「筆者の意見を問う」なら、主張と根拠をチェック
- 「抜き出し」なら、キーワードに注目して読んでいく
→ 「目的をもって読む」ことで、無駄な読み飛ばしが減ります。
ステップ②:接続語と段落構成を意識する
接続語には筆者の思考の流れが表れます。
【例】
- 「しかし」「ところが」→逆説、反論
- 「つまり」「要するに」→まとめ、主張
- 「たとえば」「例えば」→具体例、補足
→ 特に逆説の後は、筆者の本音や主張が現れやすいので要チェック!
また、段落ごとの役割(問題提起→具体例→主張)を押さえて読むと、論理の流れが把握しやすくなります。
ステップ③:キーワードと繰り返し表現をつかむ
本文には、設問に直結する「重要語句」や「繰り返される表現」があります。
それらに線を引いたり、メモをしながら読むクセをつけましょう。
【例】
- 「筆者が何度も使う言葉」
- 「問いに関係しそうな名詞」
- 「強調表現(絶対に、まさに、最も など)」
→ キーワードは“設問のヒント”になることが多いです。
ステップ④:まとめ読みと確認読みをする
1回読んだだけで解こうとせず、要点だけまとめ読みしてから設問に戻るとミスが減ります。
- 「大まかな流れ→設問→根拠を探す読み直し」の2段階読み
- すぐに答えず、「なぜそう答えるのか」の理由も確認
→ “答えを出すこと”よりも、“根拠を押さえること”が得点につながります。

読解力を伸ばすには、正しい“読み方の型”を身につけることが第一歩です。本文を「なんとなく」読むのではなく、「設問に答えるために必要な情報を探しながら読む」習慣を身につけましょう。
第3章:設問形式に強くなる!
選択・記述・抜き出し問題の攻略法
この章では、よく出題される3つの設問形式―選択問題、記述問題、抜き出し問題―について、それぞれの解き方と注意点を詳しく解説します。
選択問題|「消去法」を使って正解を導く
選択肢があるからといって、必ずしも簡単とは限りません。むしろ、ひっかけ選択肢が含まれているため、正確な読解が必要です。
【攻略ポイント】
- まず設問の条件(「最も適当なもの」など)をしっかり読む
- 明らかに違う選択肢から「消去法」で減らしていく
- 根拠が本文中にあるかを確認しながら選ぶ
→ 正解の選択肢が「なんとなく合ってる」ではなく、「根拠がある」ことを重視しましょう。
記述問題|「構造」と「型」を使って書く
記述が苦手な理由の多くは、「何を書けばいいか分からない」ことにあります。
しかし、記述問題には一定の“型”があります。
【攻略ポイント】
- 理由を問う問題は「〜だから、〜である」構文で
- 「具体例+一般化」「意見+根拠」のセットで考える
- 本文中のキーワードを活用して書くと内容に一貫性が出る
→ 自分の言葉でまとめつつ、本文の表現や語句を借りることも重要です。
抜き出し問題|「正確さ」と「範囲」の意識がカギ
一見シンプルに見えて、ミスしやすいのが抜き出し問題です。
「語句の数」「文の途中から」「◯文字以内」など、形式に細かい指定があるのが特徴です。
【攻略ポイント】
- 指定語数・指定範囲を最初にチェック
- 該当しそうな文の直前と直後も含めて読む
- 書き写しの際に“文字・送り仮名”をミスらない
→ 正しい答えが分かっていても、形式の指定違反で不正解になることもあるため、注意が必要です。
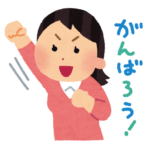
設問形式ごとの対策を知っておくことで、「どんなふうに答えるか」の指針が見えてきます。選択肢では消去法、記述では構成と語彙、抜き出しでは形式ルール――それぞれの型を意識して、正確に対応できるよう訓練していきましょう。
第4章:語彙力と文脈力がカギ!
読解を支える「ことばの力」の伸ばし方
いくら読み方のテクニックを学んでも、言葉の意味や使い方を知らなければ、本文の内容を正確に理解することはできません。
この章では、読解力を裏から支える「ことばの力」の育て方をご紹介します。
語彙力が弱いと「読み違え」が起こる
【例】
- 「皮肉」とは?
- 「逆説」とは?
- 「主張」「対比」「論点」など、読解で頻出の語句を知らないと、文意の把握にズレが出てしまいます。
→ “なんとなくの解釈”は、選択ミス・記述のズレに直結します。
【対策】
- 読解に特化した語彙帳(中学生・高校生向け)を活用
- 問題演習中に出会った語句をメモして「自分用語彙ノート」に
- 類義語・対義語もセットで覚えると理解が深まる
文脈理解力とは「前後関係で意味を推測する力」
知らない言葉が出てきても、前後の文脈から意味を予測することができれば、読解の精度は落ちません。
【例】
「彼は“おざなり”な態度を取った」
→ 文脈から、「いいかげん」「形式的」といった意味が見えてくる
【トレーニング法】
- 意味がわからない言葉をすぐに辞書で調べず、前後関係から意味を予想してから調べる
- 自分で文をつくって使ってみる
- 読書習慣を通して自然と語彙の使い方を身につける
読書と語彙の関係
語彙力と読解力を同時に鍛えるのに最も効果的なのが「読書」です。
小説だけでなく、論説文・エッセイ・評論など、さまざまな文体に触れることで、表現の幅や文脈の読み方が磨かれます。
【おすすめ】
- 1日10分でも読書習慣を続ける
- 本の中から知らない言葉をピックアップして語彙ノートに
- 本文の主張や筆者の意図を“自分の言葉”でまとめてみる

語彙力と文脈力は、「読めるか読めないか」を大きく左右するカギです。
表面的な文章だけでなく、その背景やニュアンスをつかむ力を育てるには、日々の語彙習得と、文脈を意識した読み方の訓練が欠かせません。
第5章:本番に強くなる!
模試・入試で読解力を発揮する実践トレーニング法
読解力は「知っている」だけでは身につかず、「使う練習」を通して初めて“本番力”になります。
この章では、定期テスト・模試・入試で成果を出すための実践的なトレーニング法をご紹介します。
演習のカギは「反復と分析」
読解問題に慣れるには、毎週1~2問のペースで演習を繰り返すことが大切です。
しかし、解くだけでは力はつきません。大事なのは「間違いの分析」です。
【ポイント】
- なぜその選択肢を選んだのか?
- 本文のどこを読み落としたか?
- 根拠をどう読み取れば正解できたか?
→ “読み方の癖”や“弱点”を意識することで、次からのミスが激減します。
タイムトライアルで処理力を鍛える
テスト本番では時間との戦いです。
限られた時間で確実に解くには、時間を計って演習するトレーニング(タイムトライアル)が効果的です。
【おすすめ】
- 10分で短文1問、20分で評論文など、時間設定をして解く
- 時間オーバー後に「なぜ時間が足りなかったか」を振り返る
- 毎週決まった曜日に取り組むと習慣化しやすい
本番形式に慣れる「過去問活用法」
過去問は、「出題傾向」と「自分の弱点」を発見する最高の教材です。
【使い方】
- 初見で解く(時間設定あり)
- 解いたあとは全設問について“根拠のある答え”を検証
- 自信があったのに間違えた問題に注目して分析
→ 特に“記述問題の表現のクセ”は、過去問でつかむのが一番です。
間違いノートで「読解の型」を身につける
「自分のミスの傾向」「解答の構造」「読解パターン」をまとめるノートを作ることで、復習効率が上がります。
【記録する内容】
- 問題文と設問のポイント
- 自分の解答と模範解答の違い
- 使えそうな語彙や表現、読み取り方の型
→ テスト前に見返すことで、解き方の型が自然と頭に定着します。

読解力を“本番で発揮できる力”に育てるには、「練習→分析→修正→再挑戦」のサイクルを回すことが不可欠です。ただ読むだけ・解くだけでは身につかない「使える力」は、こうした実践と振り返りを通じて磨かれます。ここに本文
読解力はすべての学力の土台になる
英語、社会、理科、さらには数学の文章題に至るまで、すべての教科に関わる「学びの基礎力」と言えます。
だからこそ、“なんとなく読む”から“意図をもって読む”へと、読み方そのものを変えていくことが大切です。

本コラムでは、読解力に伸び悩む中学生・高校生に向けて、
- ・読解が苦手な理由とその正体
- ・読み取りの基本ステップ
- ・問題形式別の答え方のコツ
- ・語彙力と文脈力の育て方
- ・模試・入試に通用する実践的な演習法
を5つの章にわたって詳しく解説してきました。
読解力を伸ばすには、日々の積み重ねが必要です。

読解ができるようになると、文章が「読める」だけでなく、「考えられる」「伝えられる」ようになります。
その力は、テストや入試だけでなく、これからの人生のすべてに活かされていくはずです。
今日から一歩、読解力を“自分の武器”にしていきましょう!
お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 439人 に閲覧されています。
.jpg)