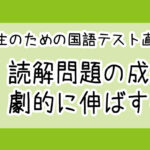「テスト直し」で成績アップ!中高生のための効果的な復習法
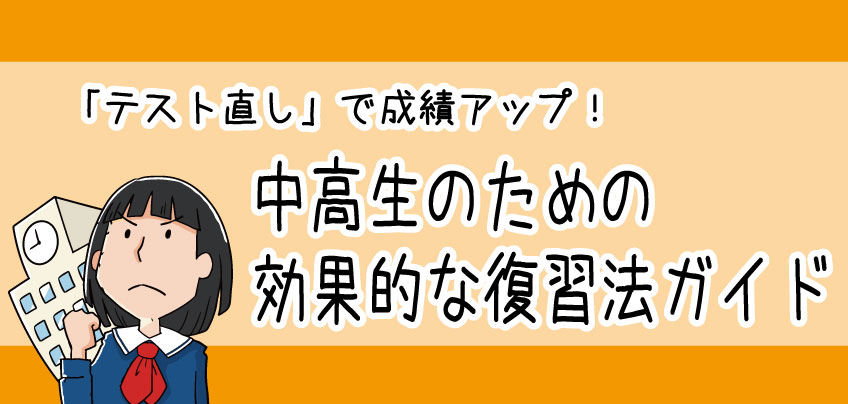
テスト直しが「次の得点」を決めるカギになる!
テストが返ってきたとき、あなたはどうしていますか? 点数だけを見て一喜一憂して終わっていませんか?実は、テストが終わった「その後」こそが、成績アップに直結する大きなチャンスです。それが「テスト直し」です。
テスト直しとは、間違えた問題を解き直し、原因を分析し、理解を深めること。単なる復習にとどまらず、「なぜ間違えたのか」「どうすれば次に正解できるのか」を明確にすることで、同じミスを防ぐことができるのです。
さらに、テスト直しを繰り返すことで、自分に合った勉強法の確立や、入試本番での“得点力”の底上げにもつながります。特に中学生・高校生にとって、日々のテストを“伸びるチャンス”に変えるためには欠かせない習慣です。

ハカセ
目次
第1章:なぜ「テスト直し」が重要なのか?
ミスには必ず「原因」がある
テストのミスには、必ず理由があります。
- 単なる計算ミスや見落とし
- 問題文の読み違い
- 知識の抜けや理解不足
- 解答時間が足りなかった など
これらを放置してしまうと、同じような問題で再び間違える確率が高くなります。テスト直しとは、こうした「間違いの原因」を明らかにし、対策を立てる作業です。
テスト直し=「学力の穴をふさぐ」作業
テストで点が取れなかった部分は、自分の“弱点”そのもの。逆に言えば、そこを埋めていけば、確実に点数は伸びていきます。特に入試では、1問の正解・不正解が合否を左右することも珍しくありません。
テスト直しをすることで、
- 次に同じ形式の問題が出たときに正解できる
- 似た問題でも応用が効く
- 出題傾向がつかめる
- 自分に足りない知識や力が見えてくる
といった“学習の質”が大きく向上します。
テスト直しを「当たり前」にする生徒が伸びる
成績が安定している生徒は、テスト後に「なぜ間違えたのか」「どうすれば次はできるか」を考えています。これはただの勉強以上に、自分の勉強を“振り返る力”=学習力を高めることにつながります。
そして何より、テスト直しには「成功体験」が生まれやすいというメリットもあります。前回ミスした問題が、次のテストでは解けるようになっている——この経験が、生徒に自信を与え、モチベーションを高めてくれるのです。
テスト直しは「できなかった自分」と向き合う作業ですが、それは次に「できるようになる自分」をつくるための第一歩。

ハカセ
第2章:効果的なテスト直しのステップとポイント
ステップ①:まず「できなかった原因」を分析する
間違いの種類を見極めることが、直しの出発点です。以下のように分類してみましょう。
- ケアレスミス(計算ミス・マークミスなど)
- 問題文の読み間違い(設問の意図を取り違えた)
- 知識不足(公式や用語を覚えていなかった)
- 応用力不足(解き方がわからなかった)
→ ただ「間違えた」で終わらせず、“なぜ間違えたか”を一問ごとに書き出すと、学びが深まります。
ステップ②:解き直しを「自力」でやり直す
答えを見て納得するだけでは意味がありません。解き方や考え方を確認したら、もう一度、自力で最初から解いてみることが大切です。
- 解法の流れを自分の言葉で説明してみる
- 式の書き方や単位、語句など細かい点も丁寧に確認する
→ 解き直しをすることで、“できるつもり”と“本当にできる”の違いが明確になります。
ステップ③:「次にできるようにする」工夫をする
間違いの内容や自分の苦手傾向に合わせて、次回に活かせる対策を考えます。
- よく間違える問題は別ノートにまとめておく
- 同じ形式の問題を追加で解く
- 暗記ミスはカードやチェックリストにして復習用に使う
→ これにより、“一度解けなかった問題”が“次は確実に解ける問題”に変わります。
テスト直しは「その日のうち」が理想!
できればテストが返ってきたその日のうちに直すのがベスト。記憶が新しいうちに見直すことで、なぜ間違えたのかの感覚が残っており、原因分析もしやすくなります。
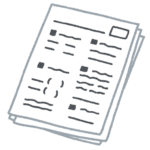
正しいテスト直しのステップを習慣化することで、テスト後の時間が“最も伸びる時間”になります。

第3章:科目別・間違いのタイプ別の対処法
国語:設問の“意図”を読み取る練習を
国語では、「本文は読めたけど設問でミスをした」というケースがよくあります。
- 記述問題→“何を答えるべきか”のキーワードを取り違えていないか
- 抜き出し問題→答えの位置が見つからない原因はどこにあったか
【対処法】
- 正解の根拠を本文中にマーカーで引く
- なぜその選択肢が誤りだったのか、自分の言葉で説明する
数学:ミスの“種類”に注目する
数学では、同じ単元でも「ケアレスミス」と「理解不足」とで直し方が異なります。
- ケアレスミス→計算過程を見直し、どこで間違えたか明確にする
- 解法の誤り→別の解き方や、類題を使って練習し直す
【対処法】
- “途中式”を省略せずに丁寧に書き出して再確認
- 間違えた問題を「似た問題」とセットで解く
英語:文法・単語・読解で直し方を分ける
英語は、以下の3パターンで直し方が異なります。
- 文法ミス:ルールの確認と例文暗記
- 単語ミス:スペルと意味のセットで再記憶
- 読解ミス:本文を精読し、根拠を明示する練習
【対処法】
- 間違えた単語・文法をカードにまとめる
- 読解問題では「なぜその選択肢を選んだか」を必ず書く
こ理科・社会:用語と因果関係の理解を意識
知識系科目では、「言葉は聞いたことあるけど説明できなかった」ミスが多く見られます。
【対処法】
- 間違えた用語を一問一答形式で復習
- 図や表を使って、用語の意味や関係性を視覚的に整理する

各教科・タイプごとに直し方を変えることで、“効率よく”“深く”理解する学習が実現します。

第4章:「テスト直しノート」の作り方と活用法
どうして「ノート化」が効果的なのか?
- 間違いの傾向が見える
- 自分の苦手が一目でわかる
- テスト前の“見直し資料”として活用できる
- 入試前に「自分専用の復習教材」になる
→ つまり、“一度のミス”を“何度でも学べる”教材に変えることができるのです。
基本の書き方ルール(テンプレート)
1問ごとに、以下のように整理して書くのがおすすめです。
① テストでの問題番号と内容(コピーや切り貼りも可)
② 自分の答え(どこをどう間違えたか)
③ 正解と解説(教科書や解答から)
④ 間違えた理由(ケアレス?知識不足?)
⑤ 今後の対策(どう覚えるか、どんな問題で再練習するか)
→ 特に④と⑤を書くことで、“反省”から“改善”へとつながります。
色分けや付箋で「パッと見てわかる工夫」を
- ケアレスミスは青、知識不足は赤など、色分けしておく
- よく出る単元や苦手単元に付箋を貼る
- ミスが多いページには★マークをつける
→ 見直すときに迷わず重要ポイントにアクセスでき、復習効率が上がります。
教科別に分ける?ノート1冊でまとめる?
- 中学生:1冊に全教科をまとめ、日付順に整理する方が継続しやすい
- 高校生:教科別にノートを分けると、専門性の高い復習がしやすい
→ 学年や学習スタイルに合わせて、自分に合った形にカスタマイズしましょう。

「テスト直しノート」は、単なる復習記録ではありません。
“自分の学習履歴”であり、“成績アップの地図”でもあるのです。

第5章:入試本番で差がつく!テスト直しの応用術
間違いを「出題パターン」として記録する
入試問題には、定期テストで出された問題と似た形式が数多く登場します。
例えば、
- 数学の文章題の設問順
- 理科のグラフ読み取りパターン
- 社会の資料問題の問い方 など。
【活用法】
「このタイプの出題では、いつもミスする」→ という“自分パターン”を見つけて、入試直前期に集中対策ができます。
直しノート=入試前の「最終チェックリスト」
定期テストで直した問題をノートにまとめておくと、入試前には「どこを見直せばよいか」が一目でわかります。
- 繰り返しミスがある単元
- 応用に弱い問題形式
- 自分だけが間違えた設問
→ これらは、得点差がつく“落とし穴”です。本番直前に見直すことで、ケアレスミスを未然に防ぎ、冷静に対応できます。
テスト直しは「自分だけの入試問題集」
市販の問題集も大切ですが、「自分が実際に間違えた問題」は、最も必要な学習素材です。
- 定期テストや模試の見直しを重ねたノート
- 自分なりの解き方や弱点対策が書き込まれたページ
→ これが「合格力」を支える基盤となります。
成績が伸びる受験生ほど「直し」に強い
最終的に差がつくのは、「できた問題」ではなく「できなかった問題への向き合い方」です。テスト直しを習慣にしてきた受験生は、本番でも“落ち着いて、冷静に解き直せる力”を持っています。
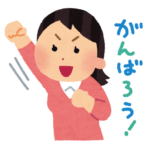
テスト直しは単なる反省ではなく、「合格する力」を身につけるための戦略的な復習法です。
テストは受けたあとが本番。
今回のコラムでは、
- テスト直しの意義
- 正しいやり方
- 科目ごとの工夫
- ノートの活用法
- 入試対策への応用
までを5つの章で詳しく解説しました。特に、直しノートの継続的な記録や、間違いパターンの分析は、受験直前の“最強の見直し資料”にもなります。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 2,289人 に閲覧されています。
.jpg)