高校古文の活用マスター講座|動詞・形容詞・形容動詞を極めてテストを攻略!
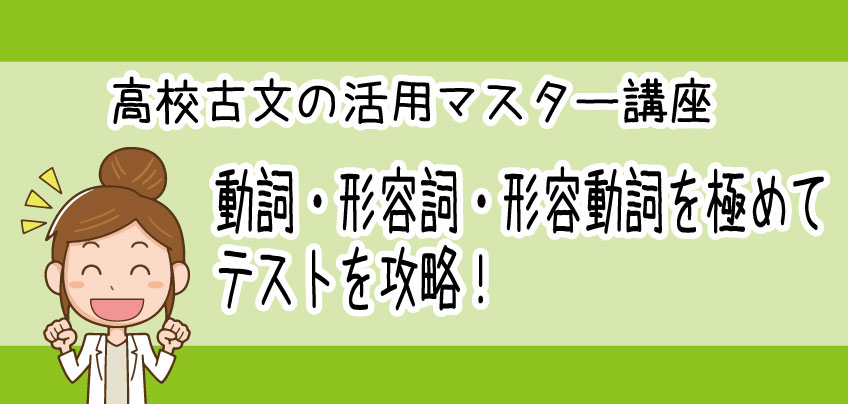
目次
【古文が苦手な高校生へ】
活用の理解が読解力アップの鍵!
「古文って何を言ってるか分からない…」
「活用表を覚えても、テストになると役立たない…」
そんな悩みを抱えていませんか?高校の国語、とくに古文は、文法知識が読解の前提になります。そしてその文法の中核にあるのが「活用」の理解です。

中学校で習う現代文法とは違い、古文特有の活用表や言い回しに戸惑う生徒も多いはず。ですが、ポイントを押さえて繰り返し練習すれば、誰でも確実に身につけられます。今回のコラムでは、「動詞・形容詞・形容動詞」という古文の基本的な品詞に絞り、テストや入試で点を取るための知識と学習法を体系的に解説していきます。
今後の学習や読解力アップに直結する「古文の活用」。
今ここでしっかり理解を深め、得点源に変えていきましょう!
第1章:古文の基礎は動詞の活用から
四段活用は古文で最も登場頻度が高い
古文で最も多く見られるのが「四段活用」です。これは、未然・連用・終止・連体・已然・命令と、六つの活用形すべてで語尾が異なるのが特徴です。例えば「書く」は、「書か・書き・書く・書く・書け・書け」と変化します。語幹の「書」は変わらず、語尾だけが変わるのが基本です。出題率が高いため、最優先で覚えておく必要があります。
→ 四段活用:語幹+「a・i・u・u・e・e」の音に変化
上一段・下一段活用の見分け方
次に押さえたいのが、「上一段活用」と「下一段活用」です。上一段活用には「着る」「見る」「似る」などがあり、「み・み・みる・みる・みれ・みよ」と活用します。語幹が変化せず、すべて同じ母音「イ段」で始まるのが特徴です。一方、下一段活用の代表例は「蹴る」で、「け・け・ける・ける・けれ・けよ」と活用し、連用形が「エ段」になる点で見分けがつきます。見分ける際には、活用語尾が一致しているかをチェックすると良いでしょう。
→ 上一段活用:語幹+「i・i・iる・iる・iれ・iよ」の音に変化
→ 下一段活用:語幹+「e・e・eる・eる・eれ・eよ」の音に変化
カ変・サ変は特殊だからこそ要チェック
最後に覚えておきたいのが「変格活用」です。「来(く)」のように活用が不規則なものは「カ行変格活用(カ変)」、「す」「おはす」のような語が「サ行変格活用(サ変)」にあたります。例えば「す」は、「せ・し・す・する・すれ・せよ」と活用し、語尾が独特です。頻出語なので、丸暗記しておきたいところです。
動詞の活用を理解することは、古文読解の第一歩です。特に四段活用は最頻出のため、最初にマスターしましょう。その他の活用も、語尾のパターンに注目すれば効率よく覚えることができます。問題演習で実際に活用形を分類する練習を重ねることで、テストや入試でもしっかり得点できる力がついていきます。
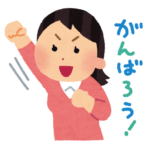
第2章:形容詞の活用で文のニュアンスをつかむ
形容詞の活用の基本は“ク活用”と“シク活用”
古文の形容詞には、基本的に2つの活用パターンがあります。それが「ク活用」と「シク活用」です。たとえば「高し」はク活用で、「く・く・し・き・けれ・〇」と活用します。一方「しるし(顕し)」のように、意味を強調する語はシク活用で、「しく・しく・し・しき・しけれ・〇」となります。活用の形は現代文法とは異なり、文中で形が変わるため、活用表は暗記が必須です。
→ ク活用:語幹+「く・く・し・き・けれ・〇」に変化
→ シク活用:語幹+「しく・しく・し・しき・しけれ・〇」の音に変化
語尾の形で活用を見分ける
ク活用とシク活用の違いを見分けるには、連用形と已然形の形に注目するのがポイントです。たとえば、「高く」と「しるしく」のように、「く」「しく」で終わる語は連用形です。また、已然形では「けれ」「しけれ」など、語尾に「けれ」が含まれていれば形容詞である可能性が高いと判断できます。入試では、文章の中で形容詞の活用形を指摘させる問題が出るため、しっかり練習しておきましょう。
形容詞の意味と用法を押さえる
古文の形容詞は、意味が現代語とはやや異なることがあります。「をかし」は「風情がある」「趣がある」と訳され、「うつくし」は「かわいらしい」となります。現代語の感覚で読むと誤読してしまうため、古文独特の意味を覚えておくことも重要です。また、形容詞がどの名詞を修飾しているかを把握することで、文全体の流れをつかみやすくなります。
形容詞は、古文における情景や人物の印象を描写する重要な語です。ク活用とシク活用を区別し、それぞれの活用形を正確に覚えることが、得点アップへの近道です。また、古文特有の語義に慣れることで、読解問題でも高得点を狙えるようになります。古文の世界に少しでも親しみを持ち、自信をもって読めるようになりましょう。

第三章:形容詞の活用を極めよう
意味と形を同時に押さえる!
活用の種類は二つだけ!
形容詞には「ク活用」または「シク活用」という、2種類の活用があります。基本的な活用形は以下のようになります。
- 未然形:く/しく
- 連用形:く/しく
- 終止形:し
- 連体形:き
- 已然形:けれ
- 命令形:〇(命令形は基本的に存在しません)
例えば「高し(ク活用)」の場合:
- 未然形:高く
- 連用形:高く
- 終止形:高し
- 連体形:高き
- 已然形:高けれ
- 命令形:〇
「美し(シク活用)」も、形は異なりますが、活用のパターンはほぼ同じです。
活用のコツは語幹を意識すること
形容詞の活用を覚える際は、「語幹」と「語尾」を分けて考えると理解しやすくなります。たとえば「高し」では「高」が語幹、「し」が語尾です。活用していく中で、語尾の形が変化しても語幹は不変であることを意識して練習すると、応用が効くようになります。
また、活用語尾の後ろに助動詞が続く場合もあるため、文中での使われ方に注意しておくと、より深い読解力につながります。
テスト対策には表の暗記と例文練習!
テストで問われる形容詞の活用は、活用表そのものが出題されるほか、適切な活用形を選ぶ問題、文法的な意味を理解しているかを問う読解問題など多岐に渡ります。表をしっかり覚えることに加え、実際の古文の中で使われている例文に触れてみることで、記憶の定着と実践力の強化が期待できます。
形容詞を味方につけて得点アップ!
形容詞は種類が少なく、活用も比較的シンプルであるため、確実に点数を取れる単元です。基本的なク活用とシク活用の形を押さえ、語幹を意識して繰り返し練習すれば、古文の読解が格段に楽になります。コツコツ積み上げて、文法問題に強くなりましょう!

第四章:形容動詞の活用を制覇しよう
「なり」「たり」で終わる言葉に注目!
形容動詞は、古文で状態や性質を表すときに使われる語で、終止形が「なり」「たり」で終わることが最大の特徴です。現代語の「静かだ」「元気だ」に相当する語が、古文では「静かなり」「元気なり」などと表現されます。
活用の基本形を確認しよう
形容動詞の活用には「ナリ活用」と「タリ活用」の2種類があります。ただし、学校で学ぶ大半はナリ活用が中心です。
代表例:「静かなり(ナリ活用)」「堂々たり(タリ活用)」
ナリ活用の活用表:例「静かなり」
- 未然形:静かなら
- 連用形:静かに / 静かなる
- 終止形:静かなり
- 連体形:静かなる
- 已然形:静かなれ
- 命令形:静かなれ
「に」「なる」「なり」など、形が似ていて紛らわしいですが、慣れると見分けがつきやすくなります。
語幹と語尾を分けて覚える
形容動詞も形容詞と同じく、「語幹」と「語尾」に分けて覚えることが大切です。たとえば「静かなり」は、「静か」が語幹、「なり」が語尾です。形容詞と異なり、語幹が名詞的であることもポイントです。
また、「に」や「なる」などの活用形は、助詞や助動詞との見分けがつきにくいこともあるため、文中での使われ方を意識して読み解く力も養っていきましょう。
実践練習で差をつける!
形容動詞の活用は出題頻度が高く、形式的な知識だけでなく、文中の文脈から正しい形を選ぶ力も問われます。
練習問題で活用形を使った空欄補充や文法識別にチャレンジしながら、理解を深めていきましょう。特に、終止形と連体形の違いをしっかりと区別することがポイントです。
見分けづらさに惑わされず、着実に覚えよう!
形容動詞は、形容詞と似ている部分がある一方で、名詞のような語幹を持ち、助詞や助動詞との区別が難しい特徴もあります。しかし、活用パターンは限られており、繰り返し演習を行えば必ずマスターできます。得点源として自信を持って臨みましょう!

第五章:古文文法の知識を使った実践的トレーニング
「知ってる」から「使える」へステップアップ!
よく出る設問パターンを知っておこう
定期テストや模試、入試などでは、次のような出題パターンがよく見られます。
- 活用形を答えさせる設問(例:「〇〇」の活用形は?)
- 活用表を完成させる空欄補充
- 活用形の識別問題(例:「〜なれ」は何の活用形か?)
- 活用形の識別と文法的な役割の両方を問う設問
特に識別問題は、助動詞や助詞との混同を狙ったひっかけも多く、深い理解が求められます。
音読+書き取りで定着!
文法知識は、頭で理解しただけでは使いこなせません。おすすめは「音読+書き取り」のトレーニングです。
たとえば「白し」という形容詞の活用を、声に出しながらノートに書いてみる。
- 「白く・白し・白き・白けれ・白かれ……」
このように耳と手を使って覚えると、記憶の定着率がぐんと高まります。
ミニテストで「できた」を確認
単元ごとにミニテストを実施するのも効果的です。短時間で復習ができ、理解度の確認と弱点把握に役立ちます。
- 例題:次の活用形を答えよ。「清し(終止形)→?」
- 例題:次の語の語幹と語尾を分けて答えよ。「静かなり」
このような問題に日常的に触れることで、文法が確実に身についていきます。
本番を意識した文章読解への応用
文法問題だけでなく、長文読解の中で文法知識を使う場面も増えていきます。文中に出てくる動詞・形容詞・形容動詞の活用形を見つけ、文の意味にどう関わっているかを考えることで、読解力そのものも向上します。
「覚える」から「使える」へのシフトが合格への鍵!
文法知識を活用するためには、日々の演習と定着確認が欠かせません。ただ暗記するのではなく、使える知識として身につけることが、テストで得点するためのポイントです。「できた!」という自信が積み重なれば、古典の学習もぐっと楽しくなります。次章ではその集大成として、文法と内容理解をつなぐ読解の方法について紹介します。

第六章:文法力を読解力に変える!
古文の点数アップ術
文法の知識を使いこなして得点力を高めよう
これまで学んできた動詞・形容詞・形容動詞の活用を「読解」にどうつなげていくかが、古文の得点を大きく左右します。ここでは、文法力を読解力へと変換し、実際の問題で高得点を狙うための方法を紹介します。
主語の推定に文法知識が活躍!
古文では主語が省略されることが多く、読解が難しく感じる原因の一つです。しかし、文法知識があれば「誰が」「どうした」を見極めやすくなります。
- 敬語表現 → 主語が「身分の高い人物」
- 形容詞の活用 → 感情の主が推測できる
- 動詞の意味と文脈 → 主語の行動がわかる
このように、文法が「文の骨格」を教えてくれるのです。
文法問題と読解問題はつながっている!
テストや入試では、文法知識を問う設問と読解問題がセットで出されることが多くあります。
- 文法問題で得た情報を使って正解を導く
- 逆に読解から文法の使い方を学ぶ
という「双方向の理解」が鍵です。知識と読解を行き来できるようになれば、古文が一気に解きやすくなります。
音読と訳で感覚を鍛える
文法を使って文を「読む」練習として、音読と訳出が非常に効果的です。
- 声に出すことで文のリズムや語感が身につく
- 現代語訳に挑戦することで内容の理解が深まる
特に、同じ文を何度も繰り返すことが定着に繋がります。
本番に向けた対策をしよう
入試や定期テストで差をつけるためには、出題形式に慣れておくことが大切です。
過去問演習や模試を活用し、「時間配分」「設問の読み方」「記述の書き方」なども意識しておきましょう。
知識は使ってこそ価値がある!
文法知識を読解に生かすことができれば、古文は決して難しいものではありません。「文法→構造→意味→主旨」といった流れで読み取る練習を積み重ね、得点できる読解力を育てていきましょう。

古典文法の「核」をつかんで、成績アップを目指そう!
今回のコラムでは、それぞれの品詞の活用の仕組み、種類、そして実際の読解への応用方法までを詳しく解説しました。

動詞は活用の種類が多く、最初は複雑に感じるかもしれません。しかし、基本の活用表を覚え、見分け方のポイントを押さえることで、読解力がぐんと高まります。形容詞や形容動詞も、語尾や文末の形に注目すれば、文の意味を捉えるためのヒントが得られます。さらに、それぞれの活用がどう文法問題や読解問題に出題されるかを知っておくことが、テスト本番での対応力につながります。
重要なのは、知識を「暗記」で終わらせず、「使える力」に変えていくことです。例文を音読し、活用を声に出して練習することで、自然と文の構造が見えてきます。読解の際に活用形を手がかりに主語や内容を読み取る力がつけば、古文がぐっと身近に感じられるはずです。
ぜひこのコラムの内容を活用して、
古典の世界への理解を深め、定期テストや入試で高得点を目指しましょう!
お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。
※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。
お気軽にどうぞ!!
こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。
/
この記事は 782人 に閲覧されています。
.jpg)
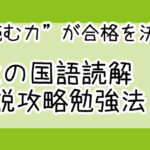
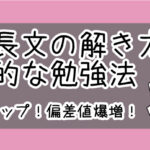
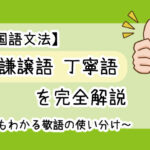

活用形の把握で文の構造を見抜く!
古文を読むときは、まず動詞や形容詞の活用形に注目します。たとえば、「行きけり」「あはれなり」「白かりける」などの語尾を見ることで、
などを見抜けるようになります。この情報が、主語の判断や場面の把握に直結します。